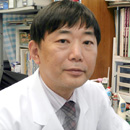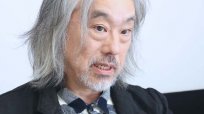肥満は短命と関係…「体脂肪率」は「BMI」より役に立つ?
肥満が糖尿病や高血圧、心臓病などのリスクになり、健康寿命を縮めることは、これまでの多くの研究により証明されている事実です。
肥満の診断のために、最も広く使われているのは「BMI」という指標です。これはキログラムの体重を、メートルの身長で2回割り算して得られる数値で、その値が25を超えると肥満と診断されています。
しかし、ポッコリお腹の人では、明らかに内臓脂肪が多そうなのにBMIは正常ということがしばしばあります。そこでメタボの検診として使われているのが、お腹回りを計測する「腹囲」という指標です。ただ、この数値は日本と海外とで基準が違うなどの問題があります。
また、体重計などの健康器具では、「体脂肪率」という数値が簡単に測定されています。
この3つの指標のうち、どれが一番健康リスクと関係が深いのでしょうか? 今年の家庭医学の専門誌に掲載された論文では、この3つの指標の比較を行っています。
アメリカで20歳から49歳の一般住民4252人を15年観察したところ、腹囲や体脂肪率の数値が高いことと、総死亡のリスクが高いこととは関連がありましたが、BMIと総死亡のリスクとの間には、そうした関連は認められませんでした。
肥満のリスクをBMIだけで判断することは、あまり科学的ではなく、腹囲や体脂肪率を含めて、総合的な判断が必要であるようです。