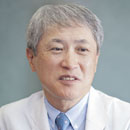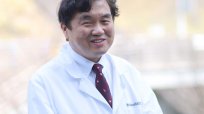「心臓周囲脂肪」は命に関わる心臓病リスクをアップさせる
肝臓の病気だけでなく、心臓病や脳血管疾患など、さまざまな病気につながる「脂肪肝」という病態を耳にしたことがある人は多いでしょう。肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積された状態を指し、食べ過ぎ、運動不足、高血糖や高コレステロールなどの生活習慣病などが原因になります。お酒の過剰摂取だけでなく、お酒を飲まない人の非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)も増えています。
脂肪肝のように、本来ならば蓄積しない場所にたまった脂肪を「異所性脂肪」といい、心臓に蓄積した異所性脂肪は「心臓周囲脂肪(EAT)」と呼ばれます。心臓の周りに脂肪が過剰にたまってしまうと、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、心不全などの命に関わる心臓病リスクが高くなるため、近年、注視されている病態です。
心臓周囲脂肪が増えると、体内の過剰な脂肪を貯蔵する役割がある白色脂肪細胞が増加して、アディポネクチンという生理活性物質の分泌量が低下してしまいます。アディポネクチンには、傷ついた血管を修復してプラークの形成や動脈硬化を抑制する作用、インスリン感受性を向上させて糖尿病を防ぐ作用、中性脂肪の燃焼を促進してHDLコレステロールを増やす作用、血管を拡張して高血圧を予防する作用などがあり、健康に有益な働きを担っています。そんなアディポネクチンが減ってしまうことで、高血糖、高コレステロール、高血圧になりやすくなり、動脈硬化が進んでさまざまな心臓病につながるのです。