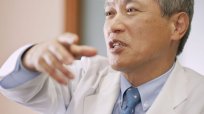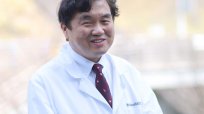体内時計が左右する“食べる時間”の科学…世界が注目の「プレジション栄養学」が描く未来
約1000人を対象に、朝食はタンパク質・水溶性食物繊維・魚の充実、夕食ではカルシウム・イソフラボンの摂取を促すなど生活リズムに合わせた栄養配分を行い、食事摂取状況や身体指標の変化を評価した。
その結果、3カ月介入で体重増加が75%程度に見られ、体重増加者は喫食率や血中アルブミン値の増加が見られた。
高喫食者は睡眠サイクル、便通・便臭、動作介助の軽減などに良い効果が表れた。シン・食事サービスは時間栄養学の社会実装の良い一例となった。
柴田氏は、プレシジョン栄養学の進化において「時間栄養学(クロノニュートリション)」が中心的な役割を担うとみている。
「これからの栄養学は、遺伝子や腸内環境だけでなく、その人の『生体リズム』まで含めて考える必要があります。同じ栄養を取っても、朝と夜では体の反応が違う。これはまさに個別化医療と同じ発想です。時間栄養学は社会実装に近づいています」
食べる内容だけでなく、「いつ食べるか」をデザインする──。プレシジョン栄養学は、未来の食卓に「時間」という新しい座標を加えようとしている。