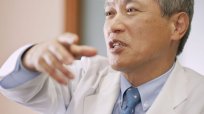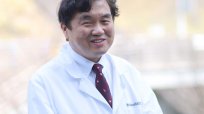体内時計が左右する“食べる時間”の科学…世界が注目の「プレジション栄養学」が描く未来
「夜型の人は朝食を抜きやすく、夕食が遅くなりがちです。結果として1日の摂取エネルギーの多くを夜に取ってしまい、肥満やメタボにつながります。一方、朝型の人は朝に代謝が活発で、栄養を効率的に使えます」
“朝少なく夜多い”パターンは、体内時計を後ろにずらす要因にもなる。
「朝にタンパク質や魚をしっかり取れば、体内時計が前進し、代謝が整いやすくなります」
■個別化医療と同じ発想
とくに高齢者では、たとえ健康な人でも加齢に伴う食欲や体重の低下により、適切な栄養の確保が課題になる。
ならば、食事のタイミングによる栄養利用効率を利用することで高齢者の低栄養を解決できるのではないか。
そんな仮説をもとに、柴田氏の研究グループは高齢者施設向け食事提供大手の「日清医療食品」と共同で、全国規模の介入研究を行った。本研究では同社が提供する省力化型の食事提供システム「シン・食事サービス」を活用し、時間栄養学の知見を取り入れたメニューを継続的に提供した。