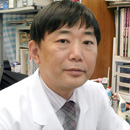「BMIが25で肥満」は誤り? 病気との関連を調べた新研究
健康診断で身長と体重を測定すると、もれなく「BMI」という数値が計算され表示されます。これは、キログラムの体重を、メートルの身長で2回割り算して得られる数値で、「体格指数」などと呼ばれることもあります。この数値が22~23くらいが、最も生活習慣病などが少ないとされていて、25以上が肥満、25以上で血圧が高いなど病気の兆候があれば、治療の必要な「肥満症」と呼ばれます。
ただし、これは日本だけの基準です。国際機関のWHOは、BMI25以上は過体重、30以上が肥満と決めています。つまり、国際的には肥満ではなく「ちょっと太り過ぎ」というくらいのBMIが、日本では肥満と呼ばれているのです。
この基準になっているのは1995年に取られたデータで、それによると主な病気のリスクはBMIが25でほぼ倍になっていました。しかしこれは、30年前の研究結果なのです。この30年で日本人の体格や栄養状態は大きく変わっています。BMIの基準も見直すべきではないのでしょうか?
今年の代謝学の専門誌に、京都府立医科大学などの研究者による、新しいBMIと病気との関連を調べた研究結果が発表されています。それによると、30年前とほぼ同様の結果もある一方で、心臓病や脳卒中などのリスクは、BMIが30を超えないと倍にはなりませんでした。
BMIが25で肥満という日本基準は、今後、見直される可能性もありそうです。