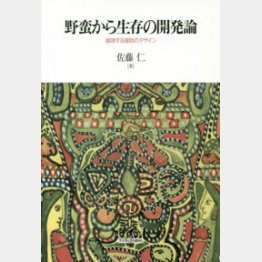地域に即して施行する実践的現場主義を
「野蛮から生存の開発論」佐藤仁著(ミネルヴァ書房 3000円+税)
本当に、「この道しかない」(自民党)のか。地方に住んでいると、中央(東京)から発せられるスローガンに反発を覚えることが多い。しかし、経済政策、エネルギー政策、安全保障政策、社会福祉政策、どれをとっても「もうひとつの道」を明確に示すことはそれほど簡単ではない。今、私たちが直面している〈危機〉は想像以上に根が深く、一時の政権や単発の政策などで克服できるものではないのかもしれない。「安全神話」や「成長神話」が崩壊したこの国で、いったい何をどう目指せばいいのか。
本書は、開発研究の学術的論文集である。しかしその射程は、いわば「新しい文明論」としても読むことが可能なほど広い。日本は、野蛮→「半開」(半文明)→文明という明治以来の単線的発展論を経て、戦後は世界有数の開発援助国となった。そして同時に現在、“援助する北”と“される南”(低開発)という二項対立を超えた、「開発以後」の諸課題にも直面している。つまり、グローバル化する現代世界では、人間の生存という共通問題の解決策を「南北の垣根を越えて地球規模で構想」しなければならなくなっている。
本書が提起するのは、単なる開発批判でも、新しい開発モデルの提示でもない。ここで蘇るのは、アリストテレスにまでさかのぼる〈実践知(フロネーシス)〉の伝統である。私たちは、それぞれの地域にとって本当は何が「貧困」で何が「豊かさ」なのか明確には分からないまま、常に手探りで「開発」を進めなければならない。このスリリングな課題に対処するためには、分業化した専門知というより、全体を見通すしなやかな総合知が必要となる。
著者によれば、このようにそれぞれの地域の現実に即して思考する実践的な現場主義という意味では、国土開発も含めた日本の開発史には普遍的な意味がある。来るべき社会のヒントは、まさに自らの足元の歴史の中にこそある。専門書で、これほど読後に爽快感が残るものは少ない。