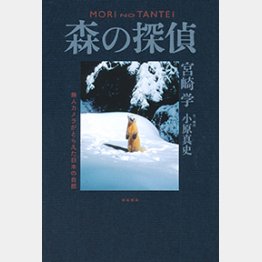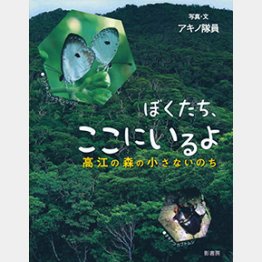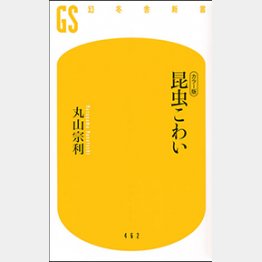生き物知られざる世界本特集
夏の暑さも一息。秋に向け植物は色づき、動物も活発に動きだす。今回は、そんな動植物たちの知られざる世界をのぞいてみよう。森の木陰で息を潜めるクマから木の葉の下でうごめく昆虫、足元で勢力を伸ばすコケの世界まで、生き物の本4冊をご紹介!
週末農園として借りた畑が、ある日何者かに掘り返されていたり、祖先の墓へのお供えものが忽然と消えていたりすると、ここで何が起きたのかと推理したくなるのは人の常。宮崎学・小原真史著「森の探偵」(亜紀書房 1800円+税)は、人間の隙をついて出没するこうした野生動物たちの生態を、日本各地に仕掛けた無人カメラに写った写真を手掛かりに明らかにしていく異色の“対話本”だ。
対話本といっても狩人のような写真家・宮崎氏の撮影現場に、興味津々のキュレーター・小原氏が同行しつつ話を引き出すという構成で、読者も宮崎と同じ現場を追体験できる。その話題も、動物の痕跡の見つけ方を皮切りに、人がつくった環境を使いこなす動物たちの生存戦略や、戦争や震災と動物との関係性など幅広い。
たとえば、冬になると人間が道に大量にまく凍結防止剤。この主成分は塩化ナトリウムと塩化カルシウムなので、この人工の塩を目当てにシカやサルが集まってくるらしい。つまり本来、塩分摂取が難しい山という環境に、車社会を築いた人間が塩分のサプリメントをまいて野生動物の健康管理をしてあげているようなものだというのだ。
また、イマドキの動物は生まれたときから人間がつくった人工物に囲まれているため、人間の出す音や光も恐れなくなってきたとも指摘。人のつくった塀の上は歩きやすいため高速道路のように使い、農家が売れない作物を同じ場所に廃棄すれば餌場として利用する。 人間は手から直接エサを与えることを餌付けだと思いがちだが、動物の目から見れば桜が立ち並ぶ公園はさくらんぼが食べられる場であり、噴水の水は一年中枯れることのない水場であり、マスの養殖場は労力をかけずに魚が捕れる狩り場となっている。
実際、宮崎氏が仕掛けたカメラの写真を見ると、テニスコートのすぐそばにクマが隠れていたり、人が犬と一緒に散歩していたすぐ後に同じ道を歩くクマが写り込んでいたりと、気づかないうちに人とクマがニアミスを繰り返していることがわかる。特に人口が減り、若者がいなくなった里山は、人の手が入らなくなった分だけ野生動物の勢力が広がっている。
人間は勝手に自分たちのエリアと動物の生息域を線引きして油断しているが、それはただの幻想にすぎない。
臨場感あふれる写真が、野生動物の真の姿を伝えてくれる。
「ぼくたち、ここにいるよ」アキノ隊員著
世界的にも珍しい貴重な生き物が残る「やんばるの森」。美しい命の宝箱のようなこの地とそこで生きる生き物たちについて、小学生でもわかるやわらかな文章と美しい写真で紹介しているのが本書だ。
絶滅危惧種に指定されているハナサキガエルやノグチゲラ、準絶滅危惧種に指定されているリュウキュウウラボシシジミなどの貴重な写真が掲載されている。著者のアキノ隊員こと宮城秋乃氏は、チョウ類の生態の研究者で、2011年から高江・安波地区の米軍ヘリパッド建設地周辺の生物分布と、ヘリパッドの建設やオスプレイの飛行が野生生物に与える影響について調べてきた。この建設のために森は切り開かれ生き物たちがすみかを次々となくしていることや、オスプレイの爆音や爆風が生態系に影響を及ぼす可能性があることにも言及。
一度失ってしまったら取り戻すことができない貴重な自然を守る必要性を、静かな語り口でつづっている。
(影書房 1900円+税)
「コケ図鑑」藤井久子著、秋山弘之監修
地球上のありとあらゆるところに進出し、他の植物なら決して生存できないような過酷な環境下でさえ生き抜く力が備わっている自然界のサバイバー「コケ」。本書は、そんな知られざるコケの世界を紹介したコケ図鑑だ。
ひとくちにコケといっても、さまざまな種類がある。たとえば街中には、乾燥や大気汚染に強い通称「アーバンモス」と呼ばれるコケたちが生息している。コンクリートや塀をつたうギンゴケ、街路樹の幹につくサヤゴケなどがその代表格だ。神社や日本庭園には、ウマスギゴケなどが鎮座し、日本アルプスの針葉樹林にはセイタカスギゴケ、岩穴にはヒカリゴケ、沢沿いの岩場にはケチョウチンゴケなどが見られるという。
本書では182種類のコケ一つ一つについて美しい写真とともに和名、学名、生息地域やその特徴を紹介。見つかりやすい確率を示した「出会い率」を星マークで表示してあるので、本書とルーペ持参で身近なコケから探索してみたい。
(家の光協会 1800円+税)
「昆虫こわい」丸山宗利著
近ごろ何かとアリが話題になっているが、著者が専門とするのは好蟻性昆虫と呼ばれるアリと共生する昆虫。この昆虫は、特定のアリと共生関係を持つ性質があるため、アリの種類が多い場所にいけばいくほど多くの種類が見つかるらしい。
著者はまだ見ぬ好蟻性昆虫を求めて、国内はもちろん、ペルー、カメルーン、カンボジア、マレーシア、ミャンマーなど世界中のありとあらゆる地面を這い回ってきた。本書は、そんな著者の研究の旅をつづった、虫捕り旅行記だ。
旅先ではまず下を向いてアリの行列を探す。行列をやっと見つけたら、その中に混じる好蟻性昆虫を見つけて採取するのだが、これが寿司の回ってこない回転寿司屋のベルトコンベヤーの前にいるようなもので、長いときには10時間以上続く行列をひたすら眺める羽目に陥るらしい。
夢中になりすぎて深夜の森で迷子になったり、恐ろしい病気を媒介するハエに刺されておびえたり、散々な目に遭いながらも昆虫探しはやめられない。かつて昆虫採集に夢中になった人なら、少年の心がうずくこと必至だ。
(幻冬舎 1000円+税)