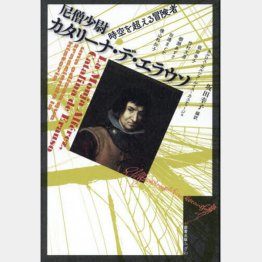「尼僧少尉 カタリーナ・デ・エラウソ」坂田幸子編訳
「尼僧少尉 カタリーナ・デ・エラウソ」坂田幸子編訳
時は16世紀末。スペイン北部の町サン・セバスティアンの良家に生まれたカタリーナ・デ・エラウソは、当時の慣習により4歳で女子修道院に入り修道生活を送る。しかし15歳のとき、脱走を実行、髪を切り、男装して男として生きることを決意。スペイン国内を放浪した後、見習水夫として新大陸へ渡る。新大陸では、スペインの征服戦争にも参加し、その活躍によって少尉の位を授けられるが、喧嘩や戦闘で何度も死に瀕し、死刑の処刑直前で恩赦を受けたり、最後に実は女性であることを明かし、故国へ戻る……まさに波瀾万丈の人生を送った。
このエラウソについての噂は、彼/彼女が帰国した1624年前後からスペイン国内で広まり、出生から帰国するまでの半生をつづった読み物が出回ったり、エラウソを主人公として戯曲も創作される。
本書は17世紀末に書き写された半生記を訳出したものに関連論考を収めたもの。半生記は一人称の「自伝」形式で書かれているが、元々本人が書いたものがあったのか、第三者が創作したのかは不明。また叙述に飛躍があったり前後の関係が不明な箇所もあるが、エラウソがたどった破天荒な冒険譚の面白さは十二分に伝わってくる。
この「自伝」は後にメキシコやスペインで映画化されたり、いくつかの翻案小説(ド・クインシーや佐藤春夫など)も生まれている。また近年ではフェミニズムの視点からエラウソの生涯が見直されてもいるという。
日本にも“帯刀の女流詩人”として知られる原采蘋(江戸後期)、儒学者で頭山満ら玄洋社のメンバーを育てた高場乱(幕末・明治初期)、男性用の二重回し姿で往診する「男装の女医」として有名な高橋瑞(明治中期)、諜報活動に従事し“男装の麗人”として名を馳せた川島芳子(昭和初期)などの男装者がいる。エラウソの生涯は、こうした男装史の先蹤をなす貴重な記録である。 〈狸〉
(図書出版みぎわ 2860円)