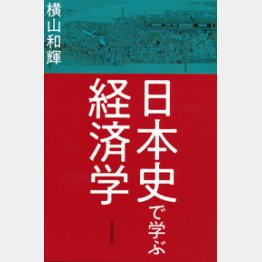「日本史で学ぶ経済学」横山和輝著/東洋経済新報社
本書は、歴史に刻まれた経済的なできごとを最新の経済学の観点から振り返り、分析するものだ。かつてマルクス経済学は、歴史学の表情を兼ね備えていたが、近代経済学が主流になるにつれ、経済学が単なる数式の羅列になってしまった。その意味で、本書は近代経済学を、歴史を通じて学ぶという斬新なアプローチを用いることによって、無味乾燥な経済学を、生き生きと楽しみながら学べるものに変えている。
本書が取り上げるテーマは、貨幣制度、特許制度、働き方改革など多岐にわたるが、私が一番興味をひかれたのは銀行危機の経済学だ。経済学でも多用される「ゲームの理論」を用いて、なぜ銀行への取り付け騒ぎが起きるのかを明快に解説している。
参考文献などを見ると、著者の論考は、奥野正寛氏や岡崎哲二氏が唱えた「戦後の日本の経済システムの大部分は、日中戦争の開戦から太平洋戦争の終戦までのたった8年間に戦時経済体制として築かれたものが、戦後も引き継がれたものだ」とする「戦略的補完性」の理論に相当影響を受けていると思われる。
ただ、奥野氏らの著作は難解だった。その後、野口悠紀雄氏が「1940年体制」という著作で、理論を分かりやすく解説したが、本書の場合は、一歩進んで、過去に起きた、そしていまだに続いている金融危機の発生メカニズムを、その防止策にまで踏み込んで、理論を応用している。
本書を本当に楽しむためには、ある程度、経済学の知識があったほうがよいと思うが、数式や専門用語を使わず、ていねいに書かれているので、素人が読んでも、十分ついていけると思う。
もちろん、本書を読んだからといって、ビジネスに役立つといった実利的メリットは、ほとんどないだろう。ただ、こうした「じわじわと面白い」本を読んで、経済の見方を培うことが、その人の教養レベルを高めることにつながるのだと思う。
いままで、経済学の教科書で挫折してきた人のなかには、本書で新たに経済学への突破口を得られる人も出てくるだろう。本書のような良書が多くの人に読まれる知的レベルの高い社会に、日本がなってくれると本当にうれしいのだが。 ★★半(選者・森永卓郎)