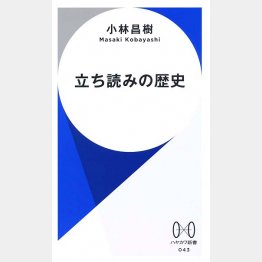「立ち読みの歴史」小林昌樹著
「立ち読みの歴史」小林昌樹著
江戸時代の本屋は、本を基本的に蔵にしまってあり、店員に出してもらい買うことになっていたので、立ち読みはできない。おまけに、江戸時代の読書は、音読が一般的で(特に庶民は)、黙読が基本の現在の立ち読みスタイルは成立しづらい。
では、書店の販売方式が、立ち読み可能な現在のような陳列販売(開架)となったのはいつ頃だったのか。江戸時代の和本(和装本)は、平積みが前提で棚にさして自由に出し入れするという行為は想定されていない。新刊本の大半が今の形(洋装本)になり、手軽に出し入れできるタテ置きは明治30年代に始まったという。
そんな出版や読書、書店などの歴史をひもとき、立ち読みという営みが、いつ、どのように始まり、現在にいたるのかを解き明かす歴史読み物。 (早川書房 1320円)