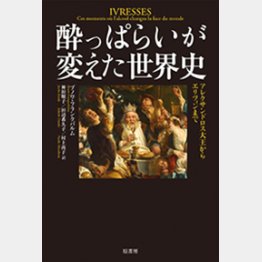「酔っぱらいが変えた世界史」ブノワ・フランクバルム著 神田順子ほか訳
緊急事態宣言が解けて、東京などでも制限付きではあるが、外でお酒が飲めるようになった。この1年半ほど、街はちょっとした禁酒法状態のような感じだったが、実際に禁酒法が施行された1920年代のアメリカと同様、あれやこれや規制をかいくぐって酒を飲む姿が散見された。ヒトはそれまでして酒を飲みたい生き物なのだ、と教えてくれるのが本書だ。
酔っぱらいの歴史が始まるのは、1000万年前のアフリカ。自然が生んだ果実酒を味わうようになった我々の先祖は、アルコールに含まれるエタノールをより速く分解できるよう遺伝子変異を遂げ、酒を好むようにプログラムされた。世界征服を企んだマケドニアのアレクサンドロス大王は酒豪として知られ、その影響があってか、部下の一行は遠征先のペルシアで酒飲み競争をやって42人の兵士が命を落としたという。
この酔っぱらい列伝に名を連ねるのは、フランスのオルレアン公(シャルル6世の弟)、オスマン帝国のセリム2世、イングランドのチャールズ2世といった面々。変わり種としては、マルクス、エンゲルスという社会主義の大立者が登場する。1844年のパリのカフェでアブサンとビールを痛飲しながら2人は意気投合し、10日間に及ぶビールの酒盛りが2人の「思想的な連携関係を深めた」。これを機に、「聖家族」「哲学の貧困」「共産党宣言」といったマルクス主義の主要著作が生み出される。
興味深いのは、アメリカ大統領のリンカーンが暗殺される前夜、警護官が酔い潰れて警護できなかったのだが、その約100年後、J・F・ケネディの暗殺前夜にもシークレットサービスの中に酒を飲んだ者がいて、警護に影響があったということだ。しかも、そのシークレットサービスを創設したのはリンカーンだった。これも酒がもたらした奇縁なのだろうか。
その他、スターリン、ニクソン、エリツィンといった政治家の酒豪ぶりがその時々の政治に影響を与えたというエピソードも語られている。まさに歴史の陰にお酒ありだ。 <狸>
(原書房 2200円)