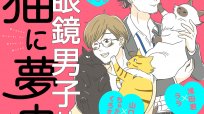市場規模は膨らんだのに…葬儀の平均単価が縮小した理由

2017年の死亡者数は134万人。出生数は94万人なので、人口の自然減は約40万人です。
死亡者数は今後、年々増え続け、人口減に拍車がかかります。当然ですが、死亡者数の増加に伴い、葬儀の件数も伸び、葬祭業者もウハウハ儲かるはずでした。
ところが、デフレ進化の影響…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り922文字/全文1,063文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。