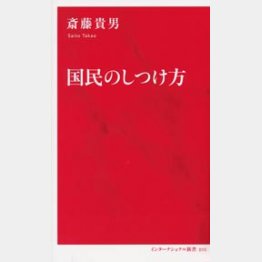だから国民は権力の理解者になってしまうのか
「国民のしつけ方」斎藤貴男/インターナショナル新書
テレビやラジオのコメンテーターをしていて、この数年、権力批判がしにくくなったことは事実だ。番組構成の面でもそうだが、何より私を含めたリベラル派が、番組に呼ばれなくなっているのだ。ただ私は、リベラルへの国民のニーズが減ったことが原因だと考えていた。テレビやラジオもビジネスだから、視聴率や聴取率が取れるのだったら、どんな主張をしていても、その人を番組に呼ぶはずだからだ。
ところが本書を読んで、考えが変わった。リベラルに対する国民のニーズが減ったのは事実としても、その国民のニーズ自体が巧妙にコントロールされていると著者が分析しているからだ。
国境なき記者団が発表した報道の自由度ランキングで、日本が世界72位に転落したという衝撃的な事実で、本書は始まる。報道の自由は、憲法で保障されているはずだが、実際には、①政府による報道への圧力②ジャーナリズム側の過剰な自主規制――によって、報道の自由が奪われている。
例えば、安倍政権に対して痛烈な批判を繰り返した元経産官僚の古賀茂明氏は、「官邸の皆さんにバッシングを受けてきた」という爆弾発言を最後に、報道ステーションのレギュラーを降板した。その後、テレビ朝日は自民党から説明を求められる。さらに高市早苗総務相が、公平性を欠く番組作りを繰り返す放送局には停波を命じる可能性があると発言する。こうした圧力に、メディアはおじけづき、「公平な」報道をするようになる。これが政府によるメディア管理の基本構造だ。
しかし、それだけではない。例えば、安倍総理はマスメディアの経営者や重鎮記者と頻繁に会食をしている。記者にとっては、その場で特別な情報を得られるからメリットが大きいのだが、総理と近づけば、当然、批判の矛先は鈍る。国民は、マスメディアというフィルターを通して世界を見ているから、メディアが権力寄りになれば、国民は簡単に権力の理解者になってしまうのだ。
ただ、唯一の救いは、政府批判を続けている著者に、書籍という発言の場所が残されていることだ。だから、政府にしつけられていない読者に、ぜひ本書を読んで欲しい。
★★★(選者・森永卓郎)