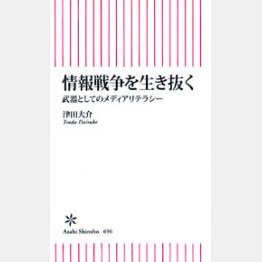「情報戦争を生き抜く 武器としてのメディアリテラシー」津田大介著/朝日新書/2018年
なぜポスト真実というようなめちゃくちゃな主張が横行し、フェイクニュース(偽情報)が現実に影響を与えるようになっているのか? この難しい問題に津田大介氏は正面から取り組んでいる。
まず、ビジネスの論理に着目する。
<ポスト真実が横行する背景には、事実をないがしろにして扇情的な情報を流し、部数やアクセス数を稼ぐメディアの存在がある。彼らにとって報じるニュースが事実かどうかは重要でない。センセーショナルなニュースを流して部数やアクセスを伸ばし、媒体に入る収入が多ければ良いのだ>と津田氏は指摘する。
資本主義社会において金儲けを否定することはできない。国や業界によるさまざまな規制が行われても、ポスト真実が金につながるという仕組みがある限り、現状は大きく変化しないと思う。
同時に重要なのは、情報を紹介する人の役割だ。
<ソーシャルメディアでシェアされる記事の信頼度は「どのメディアに掲載されているか」よりも「誰にシェアされているか」の方が重要な要素であることを示している。/「信頼できる有名人がシェアした知らないソースの記事」が表示された場合と、「信頼できない有名人がシェアした信頼のおけるソースの記事」ではどうか。結果は前者が圧倒的に支持され、信頼度で後者と倍近くの差がついたという。つまり、ソーシャルメディアの世界では、そもそもの情報の“発信者”より“紹介者”の方が情報の重み付けを決めているのだ。/ウェブの世界では「自分が一度信じた人が流す情報は本物である」という先入観が生じやすい。だから信頼のおけるメディアからあるフェイクニュースが「明らかなデマだ」と否定されても、そのフェイクニュースを信じる人が減らないのだ>との指摘が事柄の本質を突いている。
津田氏のような、優れた情報の発信者であり、仲介者である人が増えていくことが、ポスト真実やフェイクニュースが社会に与える害悪を抑制する上で重要になる。情報市場の競争で、偽情報よりも、事実と実証性を重視する情報の方が金儲けにつながるという回路を巧みに構築する必要がある。津田氏の活躍に期待する。 ★★★(選者・佐藤優)
(2019年1月18日脱稿)