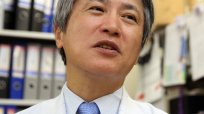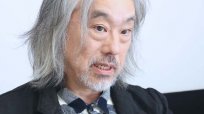てんかんの薬物療法は発作を起こさないようにする予防が目的
もうひとつ「症候性てんかん」というものがあります。これは脳梗塞や脳出血といった脳卒中、脳腫瘍などの脳の疾患がきっかけとなっててんかん発作が起こるもので、高齢者で見かけることが多いです。
通常のてんかんの場合、CTなどの画像検査では脳に異常を認めないことが多いですが、症候性てんかんの場合は脳の器質性変化が原因なので、画像検査で異常が認められることが多くあります。
冒頭でお話ししたように、てんかんの治療の基本は薬物療法です。薬物療法が効かない難治性てんかんなどでは、外科治療(焦点切除、脳梁離断など)や迷走神経を刺激する機械を脳に埋め込む治療が選択されることもありますが、この場合でも薬物療法は併用されます。
てんかんの薬物療法の目的は、てんかん発作を起こさないようにすること、つまり予防です。ただ、けいれん発作が30分以上続くか、または短い発作でも反復し、その間の意識の回復がないまま30分以上続く状態のことを「てんかん重積状態」といい、この場合、まずはてんかん発作をなんとかしなければならないため、ジアゼパムという成分の注射を行います。
また、てんかん発作が落ち着いたとしても、しばらくボーッとするような意識減損を認めることが多く、場合によってはクスリを内服できないケースがあります。その際には、抗てんかん薬の点滴投与を行うこともあります。次回もてんかんについてお話しします。