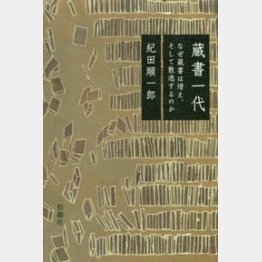本を集める真の意義は「自由」の象徴
「蔵書一代」紀田順一郎著/松籟社 1800円+税
もう40年近く前のことだが、「真空地帯」「青年の環」などを書いた作家、野間宏の東京・小石川の自宅を訪れたことがある。玄関を入るとすぐ目の前に階段がありその両側に本がうずたかく積まれていて、部屋のあちこちに本が散乱し、風呂場にまで侵食していた。家中に散らばるその本の様子は、あたかも作家の思考が脳内からあふれ出ていたかのように見えたのを覚えている。作家・研究者にとって、増殖する一方の蔵書をいかに処理するかは共通する悩みで、その苦労話も数多く書かれている。
本書の著者、紀田順一郎も希代の愛書家・蔵書家として知られているが、引っ越しのため蔵書3万冊を手放さざるを得なくなった。冒頭に置かれた「永訣の朝」には、その本の搬送が終わり、空っぽになった10畳の書斎と10畳半の書庫を直視し得ない著者の寂しげな姿が描かれている。本を愛する人にはその悲しみが痛いほど伝わってくることだろう。しかし、著者はただ悲しんでいるだけではない。そもそも個人が大量の本を蔵書することの意義とは何かという本質的な問題の解明へと向かう。それはまた、近年の日本の図書館や出版界、古書界の変容ぶりにも触れることになる。
長年にわたって膨大な量の本を収集してきた著者ならではの蔵書の楽しみや失敗談、個人蔵書の限界などが、軽妙に、時に辛辣に語られているが、印象に残るエピソードをひとつ。
戦後間もない頃、角川書店の「昭和文学全集」の内容見本に農家の主婦の投書が載っていた。その中に「多忙な農事の暇を見つけて、一生かかっても昭和文学全集、一巻づつ読んで行きたいと存じます」と書かれていた。戦争が終わってまだ生活が苦しいけれども、自由になった今、「本を読みたい」という切実な願いがここにはある。本を読むこと、本を集めることの真の意義は、この農家の主婦の言葉にあるのではないだろうか。 〈狸〉