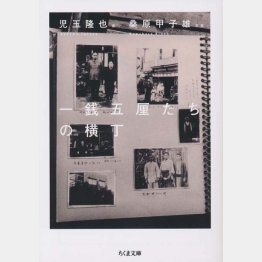奥野修司(作家)
9月×日 もう半世紀も前のことだ。大学を出たのに就職せず、趣味のカメラで生活できればと写真学校に入学した。思うまま写真を撮りながら、それにまつわる物語でも書ければ、なんて妄想でもしたのだろう。ある日、当時人気の週刊誌「平凡パンチ」に写真と原稿を持ち込んだら、なんとこれが採用されたのだ。入稿後、担当の編集者は雑談しながら1冊の本を見せてくれ、「名作ですよ」と言った。それが児玉隆也氏の「一銭五厘たちの横丁」だった。
一銭五厘というのは戦前のハガキ代で、今なら300円ぐらいだろう。このハガキ1枚で大勢の男子が召集されて戦地に送られた。江戸の面影が残る東京の下町では、出征した息子や兄弟に家族の写真を送ることになり、写真家の桑原甲子雄氏が撮影を任された。戦後30年経って、彼は写真展を開くので物語を書いてほしいと児玉氏に依頼する。とはいえ、激しい空襲で灰燼に帰した町だけに、99枚の家族写真は「氏名不詳」のまま行方知らずである。児玉氏は、ノートを片手に、路地から路地へ銃後の家族を探す旅を始める。
下町の狭い一角なのに、まるで神隠しにでもあったように彼らの姿が消えていた。地道に路地裏を歩く旅の描写は、戦中から戦後にかけて下町に生きた庶民たちの昭和史でもある。開けっぴろげで陽気で「天皇から一番遠くに住んだ」彼らの生活が浮かぶようだ。それを描く児玉氏の、恥ずかしそうに斜に構えたような文章が好きで、何度も読み返した。児玉氏には立花隆氏と並んで田中角栄内閣を倒すきっかけになった「淋しき越山会の女王」(中央公論新社 1430円)がある。でも私はこの作品の方が好きで、いつかこんな作品を書きたいと思いながら、気がつけばカメラを捨ててノンフィクションの世界に入っていたのである。
本書の初版は1975年だが、今年の5月、新たに文庫本として復刊された(筑摩書房 1100円)。久しぶりに読んだが、名作は時を経ても今も輝きを放っていた。