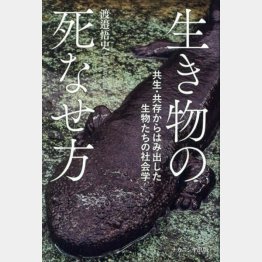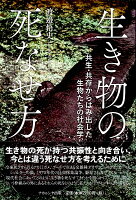「生き物の死なせ方 共生・共存からはみ出した生物たちの社会学」渡邉悟史著
「生き物の死なせ方 共生・共存からはみ出した生物たちの社会学」渡邉悟史著
今年はクマの出没が多発し、山林だけでなく市街地などでもクマによる被害が数多く報告されている。そのためクマの駆除を実施した各自治体に対して、地域外などから苦情が殺到して混乱を招いている。苦情の多くは無責任で感情的な罵倒なようだが、そこには人間中心主義を排してほかの生き物との共生・共存を目指すべきだという思いがあるのも確か。本書はそうした方向とはあえて逆向きに、共生・共存しえないことの絶望から、人は生き物をどのように死なせているのか考えていこうというもの。
最初に紹介されるのは、アカミミガメの死体がぎっしり詰め込まれている冷凍庫を前にしたある淡水ガメ研究者の「なんでカメ好きの僕がこんなことをしなきゃならないんだよ」というひと言。アカミミガメは条件付特定外来生物に指定されていて、カメを愛してやまない研究者は一方で駆除活動も行っていたのだ。冷凍処理というカメにとって苦痛が少ない殺し方をとったとはいえ、そこに割り切れない思いがあるのは間違いない。
こうした不条理は、特別天然記念物に指定されている在来のオオサンショウウオの絶滅を防ぐために、外来との交雑オオサンショウウオを廃校になった小学校のプールに収容する事業にも通じる。この場合交雑種を直接手にかけるわけではないが、自然環境から隔離することで大きな負荷をかけ死に至らせることもある。要は人間の都合で生かせる種と死なせる種という選別が行われているのだ。
そのほか、アニマルシェルターにおける保護猫の死、昆虫標本を単なる死体とみなすかどうかを巡る昆虫採集論争、吸血性のヤマビル被害を受けている地域での駆除の仕方など、一筋縄ではいかない問題が取り上げられる。
著者は言う。生き物の死や死体が働きかけてくる揺さぶり、共振性をしっかり見据えることで、新たな共生・共存の方向が見えるのではないかと。 〈狸〉
(ナカニシヤ出版 2970円)