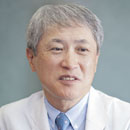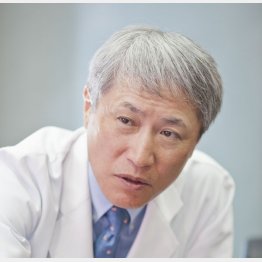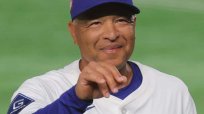先人が取り組んだ感染症対策が外科手術を大きく進歩させた
手術中の感染症を予防するためには、正しい手洗いが基本中の基本になります。医療者の手に付着している細菌が患者さんに感染して感染症を起こすと、命に関わるケースもあるからです。
いまは一般的なせっけん液で揉み洗いした後、アルコール製剤を擦り込む方法が広まってきています。かつては10分近くかけて手洗いしていましたが、3分ほどでも有効なことが科学的な検証で明らかになっています。
そんな外科医の「イロハのイ」と言える手洗いの重要性を世界で初めて訴えたのは、19世紀半ばに活躍したイグナーツ・ゼンメルワイスというハンガリー出身の医師でした。ゼンメルワイスがウィーン総合病院の産科で働いていた当時は、医療者が診察前に手を洗う習慣がなく、産褥熱の発生数や死亡率の高さが深刻な問題になっていました。産褥熱とは、産後24時間から10日以内に、2日間以上にわたって38度以上の発熱が続く熱性疾患の総称で、分娩の際に生じた傷から細菌が子宮などに入り込み、感染することで起こります。
産褥熱の原因を調査したゼンメルワイスは、医師が“感染性の粒子”を手に付けたまま患者を診ていることを突き止め、治療前に手を消毒するよう義務付けました。すると、産婦の死亡率が激減したのです。このことから、ゼンメルワイスは「医療者は次の治療に臨む前に手指衛生を徹底するべき」と訴えましたが、当時は病原菌の存在すら知られていなかったため、医学界では受け入れられませんでした。ゼンメルワイスは嘲笑の対象となり、神経衰弱に陥って不遇のまま47歳で亡くなります。