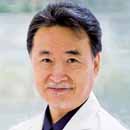「言語聴覚士」が関わる摂食嚥下機能の回復はどうして大切なのか

チームとしてリハビリ訓練を直接行うセラピストのうち、言語聴覚士(ST)は、「言葉によるコミュニケーション」に問題が生じた患者さんに対し、言語、聴覚、発声、発音、認知などの機能回復を目指してリハビリ訓練を担当します。前回、言葉によるコミュニケーション訓練と、言語を使わないコミュニ…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り1,606文字/全文1,747文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。