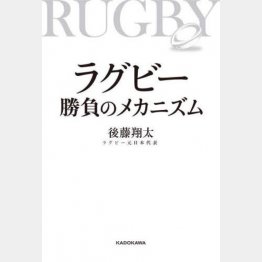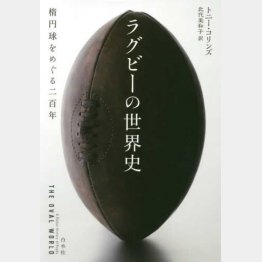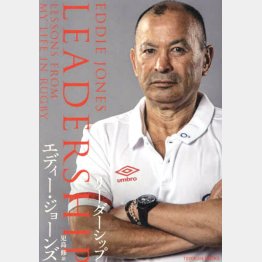ラグビー大ブーム
「ラグビー 勝負のメカニズム」後藤翔太著
ラグビーW杯人気。ルールもわからんというにわかファンだらけでも、盛り上がりは最高潮だ。
◇ ◇ ◇
「ラグビー 勝負のメカニズム」後藤翔太著
わざと点が入りにくくしているようなルールをはじめ、にわかファンにラグビーの敷居は高い。本書の著者は、早大で日本一を2度経験し、日本代表としてキャップ数8、いまは母校のコーチ兼ラグビー解説者。
本書では素人にわかりづらいラグビー競技の「基本設計」から解説してくれる。
ラグビー選手というと筋肉モリモリの体形が連想されるが、あれはスクラムを組むフォワードの選手たち。バックスは俊敏な動きと足の速さが尊ばれる。
本書がユニークなのは追手門学院大女子チームの監督として女子日本一を2度達成した経験をもとに、男ばかりのラグビーでは自分でも気づかなかった点を盛り込んだ解説になっていること。筋肉の少ない女子も男子と同じボールを使うため、男子では当たり前のパスでディフェンスを崩すことができない。それだけにボール支配率だけでなく、テリトリー(地域支配率)が決め手になるというラグビーの醍醐味が鮮明になるのだ。
女子アスリートにも注目の集まりやすい現代ならではの解説が独自の持ち味になっている。
(KADOKAWA 1760円)
「ラグビーの世界史」トニー・コリンズ著 北代美和子訳
「ラグビーの世界史」トニー・コリンズ著 北代美和子訳
ラグビーW杯で印象的なのは圧倒的なヨーロッパ勢優位の構図。南アフリカ、ニュージーランド、アルゼンチンなどはどれも欧州の影響が強い国だ。本書はイギリスの歴史学者が書いた500ページ近くにもなる大著。サッカーとラグビーに分かれる前のフットボールの時代から現代の世界中に(アメリカにも)広まったラグビーまでをたどるラグビー版グローバルヒストリーだ。
特に興味深いのは15人制とは別の13人制ラグビーの存在。日本で知られる15人制は「ユニオン」で元はアマチュア志向。対する13人制は「リーグ」でプロ志向。両者はラグビーがエリートの子弟専用から大衆向けに転換した19世紀末に分裂し、歴史的には13人制のほうが人気も高かったらしい。長く対立関係にあったため選手の移籍も不可だったが、近年では両者の歩み寄りも見られるという。
コアなラグビーファン向けともいえるが、ウンチク好きのにわかファンにもよさそうだ。
(白水社 6380円)
「LEADERSHIP」エディー・ジョーンズ著 児島修訳
「LEADERSHIP」エディー・ジョーンズ著 児島修訳
日本代表の前監督として辣腕をふるったことで知られる著者。いまはオーストラリアの監督として豪州代表メンバーの選考にも大ナタを振るったものの、1次リーグでは連敗を喫し、責任を問われていると伝えられる。所変われば品変わるのたとえ通り、ラグビーの指導法も日豪で向き不向きがあったということだろうか。
ともあれ本書は今回のW杯を前に前監督が説いた指導法の極意。内容そのものは日本の後にイングランド代表の監督を務めていた時期にまとめたもの。
「ビジョン・構築・実験・勝利・構築」という著者独自の「勝利のサイクル」は日本では上出来の成果を上げた。
その上に今の日本代表の躍進があると考えられよう。
(東洋館出版社 2200円)