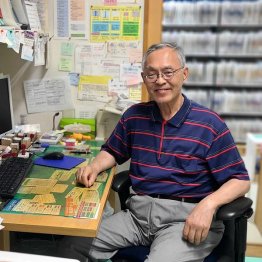(2)「最新医療」=「最先端の画期的治療」とは限らない
要は出来ることすべてをやって天命を待つというやり方である。当然、患者さんの副作用の苦痛は並大抵のものではなかったであろうと思われる。そうした治療の歴史を経て、いま、方針は大きく変わった。現在では膵がんが一定の大きさを超したら何の治療もしない、というのが基本である。その方が患者さんが安楽に日常(余生)を送れるからである。
あらゆる手法を用いる集学的治療といわれるものから、一見、消極的とも思える方法が世界共通の標準的な治療方針に取って代わるまでには、多くの時間と幾多の犠牲が払われた(今では化学療法の進歩により、さらに積極的な治療も行われているらしい)。
また、私が大学勤務時代に自分の研究テーマとして力を入れていた悪性リンパ腫もしかりである。かつては治療方針を決定する際、試験開腹(治療以外の目的でお腹を開ける)により腹腔内リンパ節の広がり所見を確認した後、放射線療法の他に数種類にも及ぶ抗がん剤の治療を行う施設もあった。
これ以外にもいくつかの診断法を基に治療法を組み合わせる集学的治療が医学界のピークに達した頃、ヨーロッパの学会を中心にもっと単純な抗がん剤の組み合わせでも治療効果はさほど変わらない、というデータが世に出始めた。やがて6種類以上を組み合わせていた化学療法は、シンプルな数種の抗がん剤を使った治療に取って代わった。結果としてこの疾患も現在ではそれほど手ごわい病気ではなくなっているらしい。