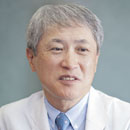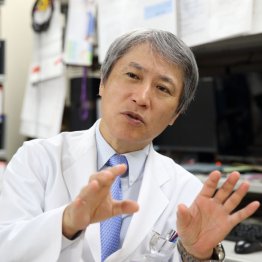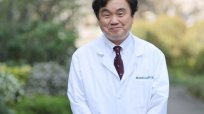感覚器と心臓(4)「老人性難聴」は心臓を害して寿命を縮める
高齢になると、音が聞こえにくくなる「難聴」を生じる人が多くなります。いわゆる「耳が遠い」と言われる状態で、「老人性難聴」とも呼ばれます。とりわけ高音域の聞こえが悪くなる特徴があり、会話の聞き取りに支障を来すケースも少なくありません。
このような難聴=聞こえにくさは、心臓にもマイナスに働き、健康寿命を縮める要因になります。会話が聞き取れないことは大きなストレスになりますし、テレビの音声や電話の呼び出し音といった生活音が聞こえにくいことによる日常生活での不便さ、車や自転車の音、人混みでの音の判別がしにくいため外出に不安を感じ、生活の質が低下してしまいます。さらに、コミュニケーションがとりづらくなって孤独や社会的孤立が深まります。
こうした聞こえにくさや孤独によって感じるストレスは、アドレナリンやコルチゾールといったホルモンの大量分泌を促し、心拍数を増加させたり血圧を上昇させるなどして、心臓病のリスクをアップさせるのです。
難聴と心臓病が密接に関わっているという報告もあります。富山大学の研究では、狭心症や心筋梗塞といった心臓血管疾患の既往のある高齢者は、難聴のリスクが約2倍に増加すると報告されています。