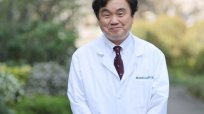災害時の避難場所を把握しておこう…高齢世帯は行動が遅れる
地震や異常気象により、自宅にとどまることに不安や危険を感じるケースが増えている。度重なる震災の経験から「避難」に関する情報は身近になったものの、誰もが正しく理解しているとは言い難い。とくに高齢世帯は体力面から行動が遅れることがある。子どもたちが定期的に情報を整理・確認し、的確に動けるよう補助しよう。
たとえば公的機関から発せられる警戒レベルの避難情報は、気象庁が発表する「早期注意情報(レベル1)」「大雨・洪水・高潮注意報(レベル2)」、市区町村長などが発令する「高齢者等避難(レベル3)」「避難指示(レベル4)」「緊急安全確保(レベル5)」の5段階。その意味を理解しているか確かめ、レベル3になれば迷わず避難行動を取るよう促したい。
ハザードマップのチェックも重要だ。これは自然災害が発生した際に想定される浸水想定区域や避難先、避難経路などを表示した地図のこと。地域にもよるが地震、火山、土砂災害、洪水、高潮、津波などに対応した種類がある。「市区町村名 ハザードマップ」で検索すればすぐに見つけることができるだろう。
さらに、市区町村名と「防災マップ」あるいは「避難先」で検索すれば、避難先の名称や住所、連絡先、規模などを把握することができる。参考までに、避難先は危険から逃れるため緊急的に避難する「指定緊急避難場所」と、一定期間避難生活が可能な「指定避難所」に大別される。