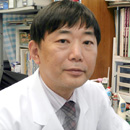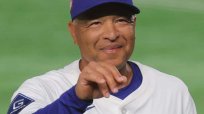甘い物が食べたくなるのは腸内細菌の乱れ? 意志の強弱は無関係
甘いお菓子やジュースは、ついつい食べ過ぎ、飲み過ぎてしまうものです。
体重が多くて、血糖が上昇しているなど、肥満症の状態にある人では、そうした甘い物を食べ過ぎてしまう傾向が強く、それが肥満の大きな原因になっていることが分かっています。
なぜ、甘い物を食べたいと思う気持ちは、それほど強いのでしょうか? 人間を含む哺乳類は、「甘い物を好む」という嗜好を持っていて、それは脳の扁桃体という部分で、コントロールされていると考えられています。ただ、甘い物を食べてそれが吸収された時に、どのような仕組みで脳に影響するのか、といった詳細はこれまであまり分かっていませんでした。
今年の微生物学の専門誌に興味深い研究結果が報告されています。甘い物に多く含まれる脂肪酸に結合する受容体が腸にあり、それが減少するとネズミは甘い物を食べたがるようになります。この受容体が減少すると、腸内細菌のうち日和見菌と言われている「バクテロイデス」という種類の菌が減少します。じつはこのバクテロイデスが、腸の血糖低下ホルモンを介して、甘い物を過剰に摂取する反応を抑え込んでいたのです。
これはまだ主にネズミの実験の結果なので、そのまま人間に当てはまるかどうかは分かりませんが、甘い物を食べ過ぎるのは、その人の意志が弱いからではなく、腸内細菌の乱れに原因があるのかもしれません。