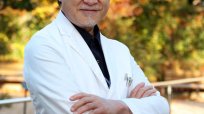(41)「お父さん、死んでしまったよ」入所の日、母にようやく伝えた
仏壇はないけれど、奥の和室に遺影が置いてある。手を合わせるかと聞くとうなずいた。いくぶん若い頃の父の写真を見つめ、「ごめんねえ、お父さん」と、はっきりした声でつぶやいた。その言葉が何を意味するのか、私にはわからなかった。雨がいっそう強くなった。
ほんの5分ほどで実家を出て、施設へと向かった。私自身もこの日が初めてだった。前日、居室に届けたカーテンや照明などはすでに整えてあった。施設の重ねての厚意に感謝した。この立ち会い以降は、面会が制限される。とはいえ、母が病院にいた頃は一切の面会がかなわなかったため、制限下でも見舞いができることでひとつ前に進んだような気がした。
翌日、叔母たちが短時間の面会に訪れ、私も立ち会った。母がもっとも気にかけ、信頼を寄せていた妹である叔母もそのひとりで、話は弾んだ。母はほとんど表情を変えることがなく、話が理解できているのかどうかわからなかったが、かすかに口元にほほ笑みを浮かべるような瞬間もあった。
その叔母は、この面会からわずか2カ月後、病気の再発によって急逝した。実家に戻ってひとりでいる私に、手作りのキャロットケーキを持ってきてくれるような優しい叔母だった。人の命の終わる順序はわからないものなのだとしみじみ感じている。(つづく)
▽如月サラ エッセイスト。東京で猫5匹と暮らす。認知症の熊本の母親を遠距離介護中。著書に父親の孤独死の顛末をつづった「父がひとりで死んでいた」。