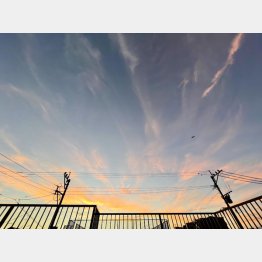(47)父との思い出話も、私の幼い頃の記憶も、もう共有できないのだ
それは父からの小さな年末の贈り物のように思えた。「最後にもらった年賀状を大切にします」と言ってくださった。父は友に恵まれていたのだと、うれしく思った。
一方で母の存在は、また別の意味で私を揺さぶっていた。日中の忙しさにかまけて、施設の母とスマートスピーカーで話す時間をとれないことがある。申し訳なさと同時に、「申し訳なさ」を私に生じさせる母への苛立ちが湧いてきて、それを感じてしまう自分への嫌悪が重なる。その繰り返しだった。
母とはもう父との思い出話も、私の幼い頃の記憶も共有できない。そのむなしさと恐ろしさ。自分の存在を支えていたはずの過去が消えかけ、私は本当にここに存在しているのかと疑うような思いにとらわれることが多くなった。
母はまだいいだろう。しかし、これからの私を受け継ぎ記憶してくれる人は、もはやいない。私にも何か残せるものがあるのだろうかと自問するが、その答えは見つからないのだった。 (つづく)
▽如月サラ エッセイスト。東京で猫5匹と暮らす。認知症の熊本の母親を遠距離介護中。著書に父親の孤独死の顛末をつづった「父がひとりで死んでいた」。