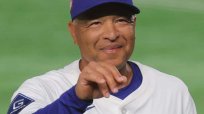膵臓がんはなぜ早期発見が難しい?「尾道方式」なら5年生存率は全国平均の約2.5倍
先進的な「膵臓がんドック」の効果
こうした臓器の位置的な要因が、膵臓がんの早期発見を難しくしている。これに対し、早期発見に向けた取り組みは各地で展開されている。
広島県の「尾道方式」では、膵臓がんのリスク因子が2つ以上ある人を対象にまず、地域連携施設でエコー検査を実施。そこで膵臓がんの疑いにつながる膵管拡張などの症状があれば、次にJA尾道総合病院で超音波内視鏡(EUS)、腹部CT(コンピューター断層撮影)検査、MRI(磁気共鳴画像装置)検査などを施行するものだ。
膵臓がんのリスク因子とは、糖尿病や慢性膵炎、膵臓がんの家族歴のある人、さらに喫煙や過度な飲酒、肥満などが挙げられる。
この尾道方式によって尾道市の膵臓がんの5年生存率は、全国平均の8.5%に対し21.4%に達したという。
早期発見に向けた取り組みは、クリニックレベルでも実施されている。前出の北青山D・CLINICは、EUSなどを取り入れた先進的な「膵臓がんドック」を提供している。
「EUSは、通常の胃カメラのような内視鏡の先端に超音波装置(マイクロエコー)を取り付け、胃の壁越しに膵臓を間近で詳しく観察します。EUSでは一般的なエコー検査で見えづらい障害を避け、膵臓を『直接なぞるように』鮮明に観察することが可能です。このため、ごく小さな病変や、前がん病変の早期診断にも威力を発揮します」(阿保院長)
膵臓がんドックでは、血液検査(腫瘍マーカー・膵酵素検査)、リキッドバイオプシー検査(膵臓がんRNA検査)も組み合わせて、膵臓がんの可能性や、膵臓の健康状態を総合的に評価する。膵臓がんドックは原則、自由診療で行われている。
膵臓がんは難治性といえども、1センチ未満の早期で見つかると5年生存率は約80%になるとされる。同クリニックではEUSを含めたドックによって、1センチ弱の膵臓がんを発見できた40代男性の症例などがあるそうだ。
(医療ジャーナリスト・大家俊夫)