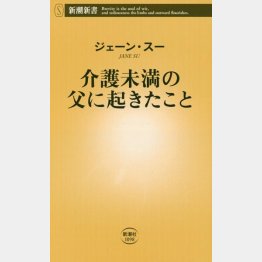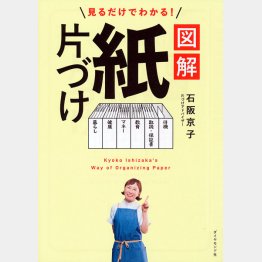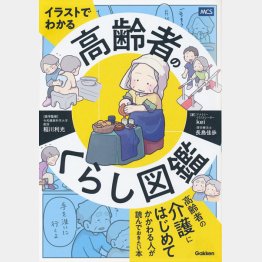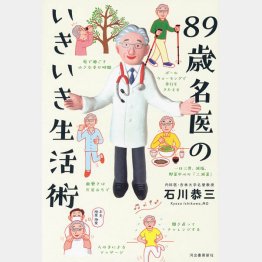備えあれば憂いなし!終活の本特集
「介護未満の父に起きたこと」ジェーン・スー著
高齢者になることは、誰にとっても初めての経験だ。自分や家族の老化に直面してあたふたしなくて済むように、役に立つ情報を仕入れておこう。
◇ ◇ ◇
「介護未満の父に起きたこと」ジェーン・スー著
著者の父は82歳の独居老人。無職の高齢者が家を借りるためには初年度に1年分の家賃を一括支払いする必要がある。著者は父の人生をさらした本を書き、印税を支払いにあてた。
社交性はあるが協調性に乏しいのでヘルパーを頼むのは難しく、父は大奥のようにガールフレンドたちに囲まれて暮らしていた。ところが最高権力者の「御年寄」が高齢化のため来られなくなった。
生活力ゼロの父の家は、着なくなった服や、よくわからない電化製品で満杯。著者は「いま、ここになくてよいもの」を納戸代わりの小部屋に移し、冷蔵庫の中身を出し、捨てられるものは捨てた。そして支援サービスを調べ、父の生活を立て直すためのToDoリストを作る。
父が介護の前段階だと気づいて、父の生活を回すために5年間、奮闘した娘の体験記。
(新潮社 990円)
「見るだけでわかる!図解紙片づけ」石阪京子著
「見るだけでわかる!図解紙片づけ」石阪京子著
チラシやDM、学校からの「お知らせ」など、とりあえず取っておいて片づけられないのが「紙」。ところが、保険の証書などが必要なのに出てこない、ということも。
「紙」を片づけるのに大切なのは「どう収納するか」ではなく「何を残すか」を知ることである。紙は〈①一見して不要な紙はすぐに捨てる ②一瞬、迷う紙は確認して捨てる ③書かれた情報だけが必要な紙は写真に撮ってスマホ保存する ④紙自体が必要な紙はファイリングする〉の分類で処理する。
その分類で必要だと認めた紙は、ファイルボックスで収納する。「健康」「取説・保証書」といった大まかな分類にすれば、必要な紙が5秒で取り出せる。
ファイルボックスや持ち出しフォルダーなどの使い方が図解で説明されていてわかりやすいノウハウ本。
(ダイヤモンド社 1650円)
「イラストでわかる 高齢者のくらし図鑑」kei&長島佳歩著
「イラストでわかる 高齢者のくらし図鑑」kei&長島佳歩著
高齢者が自宅で生活することを不安に感じるようになったとき、何が問題で、どういう対策をとったらいいのか考えるのに参考になるのがICF(国際生活機能分類)。心身機能、個人因子、環境因子などの項目をチェックして、まず問題点を把握することが必要である。
通院が大変、お金の管理が大変などの悩みがあるときに相談にのってくれる窓口が地域包括支援センター。高齢の親が離れた地で1人暮らしをしている場合でも、親が住む地域で利用できる見守りサービスや介護保険外のサービスも紹介してくれる。
同居家族がいる高齢者でも、通所施設で入浴などのサービスを利用したり、リハビリを受けることで家族の負担を軽くすることができる。
介護が必要になったら、何を利用すればいいか教えてくれる役に立つ一冊。
(Gakken 1980円)
「89歳名医のいきいき生活術」石川恭三著
「89歳名医のいきいき生活術」石川恭三著
これといった趣味もなく仕事一筋だった人が、定年退職後、急に老け込んでしまったりするのは、仕事が生きがいになっていたからではないか。孫の成長が生きがいだったりすると、孫の成長につれて生きがいが薄れてしまう。予備の生きがいをいくつか用意しておくとよい。何か新しいことをしてみようと考えを巡らせることが、気力を奮起させるエネルギーになるのだ。
著者の先輩は若い頃、ドイツに留学し、さまざまなパーティーで得意なマジックを披露して小遣い稼ぎをしていた。それを知ったテレビ局に出演を依頼され、司会者に職業を聞かれて「マジシャンです」と答え、趣味を問われて「医学です」と答えたという。こんなレベルの高い趣味をもっているのが羨ましい。
89歳の名医が認知症や老化を防ぐ日々の習慣をアドバイス。
(河出書房新社 1760円)