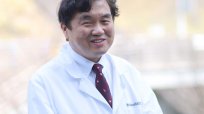在宅医療も外国出身の患者が増加…言葉の壁をどう乗り越えるか
近年、在宅医療の現場でも外国出身の患者さんが増えてきました。特に当院では、中国残留孤児やそのご家族が比較的多くいらっしゃいます。戦後80年を迎えた現在では、そうした方々のコミュニティーが存在しており、日本語と中国語の両方を話せる中国出身のケアマネジャーが、その地域の患者さんを担当することもあります。
当院で2年前から在宅医療を受けている90代の男性患者さんがいます。この方は、脳梗塞をはじめ、狭心症や糖尿病、認知症など複数の慢性疾患を抱えていました。ご本人は日本生まれ・日本育ちですが、介護の中心となっている奥さまは中国出身の方です。長年日本に暮らしているものの、日本語の会話はあまり得意ではありません。
診察時には、いつもご主人を交えて、奥さまが身ぶり手ぶりを使いながら一生懸命コミュニケーションを取ってくださいました。
「なにかきてた」(奥さま)
「それは別の訪問看護のチラシなので、対応の必要はありませんよ」(私)
このように、郵便受けに入っていた訪問看護のチラシを見せながら、「夫の療養に関係があるのでは」と確認されることもよくありました。