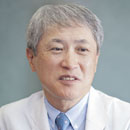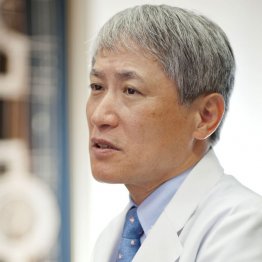感覚器と心臓(5)「難聴」がどれくらい進んだら補聴器の使用を検討するべきか
また、患者さんのお話を聞くと、ある程度の高齢になっても会社の重要な会議に出席しなければいけない人などは、内容を聞き逃したり、何度も聞き返すことが難しいため、早めに補聴器を導入するケースが少なくないそうです。
このように立場や職業など生活環境の違いによってもどのタイミングで補聴器を使い始めるかは変わってきますが、一般的には、聞こえにくさによって音を聞き逃してしまうことが、自分自身の行動を狭めたり、ストレスを増やしていないかどうかを点検して、思い当たる場合は補聴器の使用を検討する--。そんなアプローチが正解といえるでしょう。
■日本では普及率が極めて低い
私が普段から診ている患者さんからも、「最近、耳が遠くなった」「聞こえづらくなって困っている」といったように聴力の低下について相談されるケースがあります。繰り返しになりますが、難聴=聞こえの悪さは心臓にとって大きなリスクになりますから、そんなときは、私の知人で上皇陛下の主治医を務めたこともある耳鼻咽喉科の専門医を紹介して診てもらっています。そこから補聴器を使い始めた患者さんからは、「紹介してもらってよかった」と喜ばれています。やはり、日常でコミュニケーションをとる際に重要な要素である言葉を聞くという機能を、なるべく違和感がないように維持することはストレスの増幅を避けるためにも重要なのです。