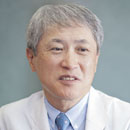健康リスクをアップさせる「肥満症」の治療について考える
ほかにも、増加した脂肪細胞からは血栓を溶かす物質を阻害する「PAI-1」、インスリンの働きを低下させたり血管内皮細胞の働きを抑えたり、炎症を引き起こす「TNF-α」、血管を収縮させて血圧を上げるアンギオテンシンのもとになる「アンギオテンシノーゲン」といった生理活性物質が多く分泌されます。これによって血管内皮が傷ついて血栓ができやすくなり、血圧も上昇して心臓病のリスクがアップするといわれています。
こうした解説を基にして、「肥満は『肥満症』という病気なので、治療が必要である」という主張が広まってきました。2000年に日本肥満学会が中心となって提唱した考え方で、近年、肥満症の治療薬として「ウゴービ(一般名:セマグルチド)」や「ゼップバウンド(一般名:チルゼパチド)」が承認されたこともあって、さらに進んでいます。
単に太っている状態を指す肥満とは異なり、BMIが25以上で、かつ肥満を原因とする健康障害がある場合に肥満症と診断されます。健康障害とは、高血圧、耐糖能異常、脂質異常症、高尿酸血症・痛風、冠動脈疾患、脳梗塞・一過性脳虚血発作、NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)、月経異常・女性不妊、睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群、運動器疾患、肥満関連腎臓病の11の障害です。該当する場合、食事療法や運動療法を中心にした治療が行われ、肥満治療薬が保険適用となるのです。